廃棄パソコンから情報漏えいを防ぐために。「データ消去証明書」が必要な理由

古くなったパソコンを処分する際、「初期化したから大丈夫」と思い込んでいませんか。実際には、適切なデータ消去を行わなければ、機密情報が簡単に復元されてしまうことがあります。こうした情報漏えいは、企業の信頼を失墜させ、時には損害賠償や取引停止に発展する深刻なリスクです。
その対策として注目されているのが、データ消去サービスとデータ消去証明書(破壊証明書)の導入です。この記事では、情報漏えいの発生要因から、証明書がもたらす安心の仕組み、そして企業が取るべき具体的な対策までを詳しく解説します。
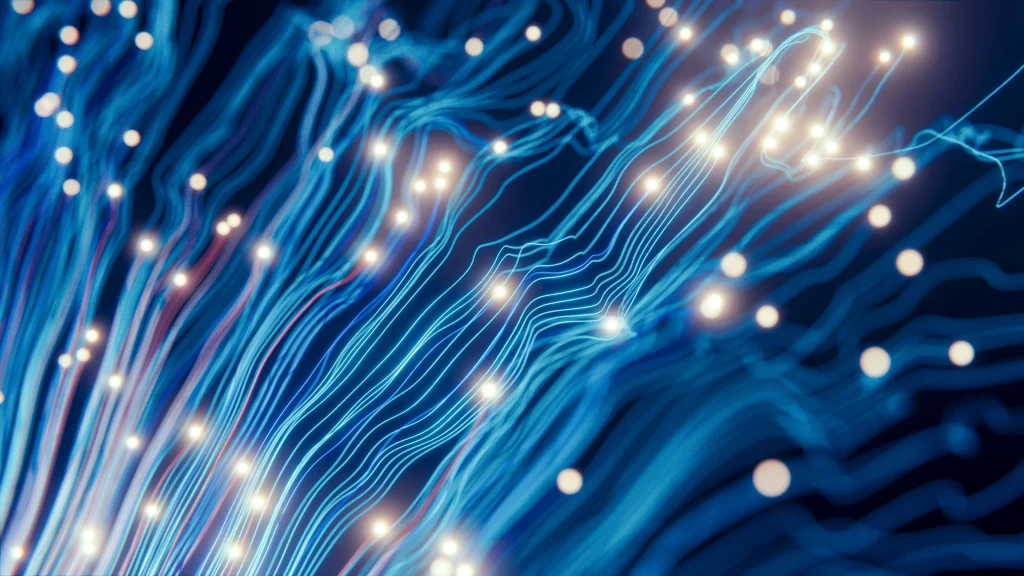
目次
廃棄時の情報漏えい、なぜ起こるのか
古くなったパソコンを廃棄した企業で、情報漏えい事件が後を絶たない状況が続いています。原因の多くは、データ消去の不備によるものです。
廃棄処理そのものは完了していても、記憶媒体内部のデータが物理的に残っているケースは少なくありません。
日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の調査によると、2023年時点で報告された情報漏えいインシデントのうち、約6.8%が「廃棄・リユース時のデータ残存」に起因していたと報告されています。この数値は一見小さく見えますが、全国の企業規模で換算すれば年間100件以上が「廃棄ミス」から発生しており、決して無視できないリスクといえます。
廃棄業者の実態と委託リスク
データ消去を外部業者に委託する場合、委託先の選定が極めて重要です。廃棄を請け負う業者の中には、環境処理を目的とした一般的なリサイクル業者もあれば、IT資産管理を専門に行う業者も存在します。しかし、両者の間にはデータ消去の品質基準に大きな差があります。
リユース業者と廃棄業者の違い
リユース業者は、回収したパソコンやサーバーを再利用・再販することを目的としており、内部ストレージを残したまま出荷するケースがあります。たとえOSを再インストールしても、ストレージ内部には残存データが残り、復元ソフトで簡単に読み取れてしまう場合があります。一方、データ消去サービスを専門に行う業者は、磁気破壊装置やデータワイプ専用ソフトを使用し、完全消去を保証します。この違いを理解せずに依頼すると、企業は知らぬ間に機密データを外部へ流出させる危険を抱えることになります。
委託先選定時に確認すべきポイント
業者を選ぶ際には、いくつかの基準を設ける必要があります。まず、ISO27001(ISMS認証)などのセキュリティ認証を保有しているかを確認することが大切です。次に、作業現場の監視体制や入退室管理の有無をチェックします。
また、データ消去後にデータ消去証明書(破壊証明書)を発行してくれるかどうかも見逃せません。これらの要素が整っていない場合、消去作業が行われていたとしても、再現性や信頼性を担保できない可能性があります。
実際に起きた情報漏えい事例
2022年には、ある中堅IT企業が廃棄業者へパソコンを一括処理で委託した際、社内サーバーのバックアップデータが入ったHDDが中古市場に流出する事件が発生しました。業者は「破壊済み」と報告していましたが、実際には物理的な破壊が行われていなかったことが後に判明しています。
その結果、顧客情報や契約データが外部へ流出し、信用失墜と多額の賠償責任に発展しました。このようなトラブルは「信頼して任せた」だけで起こり得ます。業者選定の段階で証跡を残す体制があるかどうかを確認することが、企業を守る第一歩です。
自社消去の限界と見えないリスク
自社内でデータを削除しても安全とは限りません。削除ボタンを押しただけでは、データは完全には消えず、記録領域の参照情報だけが消去される仕組みになっています。つまり、データ本体は残っており、復元ツールを使用すれば容易に取り出せるのです。
論理削除と物理削除の違い
データ削除には「論理削除」と「物理削除」があります。論理削除はOS上の削除操作であり、見た目上はデータが消えても実際には残存しています。一方、物理削除は磁気破壊・粉砕・穿孔などによって媒体そのものを破壊する方法であり、復元不可能な状態にすることができます。
企業の安全性を確保するには、論理削除だけでなく、物理的破壊と証跡管理を両立させる必要があります。その証拠となるのが、破壊証明書の存在です。
復元ツールの脅威
現在、インターネット上には無料で利用できるデータ復元ソフトが多数存在します。削除済みや初期化後のデータであっても、こうしたツールを使えば数分でファイルを再現できることがあります。セキュリティ企業の調査では、「中古パソコンの約30%から個人情報が復元可能だった」と報告されています。つまり、「削除したつもり」では不十分であり、第三者に悪用される可能性が現実的に存在するのです。
自社対応の落とし穴
自社でデータ消去を行う場合、作業記録が残らないことが最大の問題です。担当者が誰で、どの方法で消去したのかが証明できないため、外部監査や取引先からの確認に応じることができません。
個人情報保護法改正以降は、「削除した」ではなく「削除を証明できる」ことが法的にも求められています。こうした背景からも、データ消去サービスを利用し、データ消去証明書を保管することが安全対策の基本といえます。

破壊証明書・データ消去証明書が担保する「安心」
データ消去証明書(破壊証明書)は、データを完全に消去したことを第三者的に保証する正式な文書です。企業はこれをもって、「誰が・いつ・どの方法で」データを消去したかを明確に説明できます。監査・取引先対応・コンプライアンスチェックの場面で信頼を示すための根拠となり、情報管理体制の透明性を高める役割を果たします。
証明書の発行プロセス
データ消去証明書の発行には、厳格な工程管理が求められます。単に作業を終えるだけではなく、各ステップを記録・可視化することで信頼を担保します。
引取から識別番号の付与
企業から回収した機器には、シリアル番号や資産管理番号が紐づけられます。専用の管理システムに登録し、どの機器がどの時点で処理されたかを追跡できるようにします。この時点でQRコードやバーコードを貼付し、誤配送・混在を防止する体制を整えます。
こうした管理により、後からでも特定機器の処理履歴を明確に確認することができます。
データ消去・物理破壊の工程
消去の方法には主に2つあります。
1つは、ソフトウェア方式(データワイプ)で、DoD 5220.22-M方式やNSA方式といった米国防総省準拠の上書き消去を複数回行うものです。
もう1つは、物理破壊方式で、磁気破壊機や穿孔機によって記録面そのものを破壊します。
どちらの方式でも、作業はすべてシステム上でログ管理され、復元不能な状態であることが証明可能になります。
証明書の内容と信頼性
発行されるデータ消去証明書には、対象機器の型番・シリアル番号・作業日時・責任者・使用機材・処理方法などの詳細が明記されます。さらに、立会者の記録や写真データの添付が行われる場合もあります。このような詳細情報が記載されることで、企業は外部監査や顧客への説明時に「確実な証跡」を提示できます。つまり、証明書は単なる報告書ではなく、企業の信頼を支える文書なのです。
電子化とクラウド保管の動き
近年は、証明書の電子化も急速に進んでいます。PDFでの発行だけでなく、クラウド上での保管や検索も可能になりました。一部の業者では、API連携による自動登録システムを採用しており、企業の資産管理システムと連携して証明書を一元管理できます。これにより、データ廃棄履歴をリアルタイムで追跡し、内部統制を強化することができます。

中小企業が直面するIT資産管理の課題
中小企業では、限られた人員とコストの中で情報機器を管理しているため、IT資産のライフサイクルを全体で把握できていないケースが多く見られます。たとえば「どのパソコンがいつ購入され、誰が使い、いつ廃棄されたのか」という履歴が不明瞭な企業も少なくありません。経済産業省の「情報処理実態調査(2024年版)」によると、従業員100名未満の企業の約56%が「情報機器の廃棄や再利用の手順を明文化していない」と回答しています。この数値が示す通り、多くの企業では廃棄時の情報管理が属人的で、データ消去証明書の取得や保管体制まで整備できていないのが現状です。
そのため、IT資産管理を整理することが、結果的に情報漏えいの防止につながるのです。
ネットワーク機器の設定や更新の遅れ
パソコンやサーバーだけでなく、ルーターやスイッチなどのネットワーク機器も、企業の情報を守る重要な資産です。しかし中小企業では、設置後にほとんどメンテナンスされないまま、旧バージョンの設定や古い暗号化方式が放置されていることがあります。
その結果、通信の安全性が低下し、サイバー攻撃の侵入口になることがあります。
古いファームウェアが抱えるリスク
ネットワーク機器には定期的なファームウェア更新が必要ですが、古い機器ではアップデート機能が停止している場合もあります。特に2018年以降、世界的に被害を広げたVPNFilterウイルスは、ルーターやNASなどの古いファームウェアを狙って感染しました。このウイルスは通信内容を傍受し、管理者アカウントの情報を盗み取ることができるため、更新を怠ること自体がセキュリティリスクになります。企業の情報資産を守るには、ネットワーク機器も定期的に更新し、データ保護と物理的廃棄をセットで行う仕組みが必要です。
設定管理の属人化問題
中小企業では、ネットワーク管理を特定の担当者が兼任しているケースが多くあります。このような状況では、担当者の異動や退職によって、設定情報が引き継がれないままブラックボックス化してしまうことがあります。結果として、誰も設定を変更できず、障害発生時に原因が特定できないという問題が発生します。ネットワーク構成図や設定ログをデジタルで保存し、複数人で共有できる体制を整備しておくことが、情報資産を守る第一歩になります。
データ廃棄ルールと連携させる意義
ネットワーク機器にも、内部メモリに設定情報や通信履歴が残されています。ルーターやNASを廃棄する際、初期化だけではこれらのデータが完全に消去されないことがあります。そのため、パソコンと同様にデータ消去証明書を発行できる業者を選定し、機器廃棄まで一貫して管理することが求められます。データ廃棄ルールとネットワーク保守計画を連携させることで、廃棄時のセキュリティ抜け漏れを防ぐことができます。
ファイアウォール・VPN導入の遅れが招く脆弱性
テレワークが普及した今、VPN(仮想専用線)やファイアウォールは、企業の外部アクセスを守る基本的な防御線となっています。しかし、総務省の「通信利用動向調査(2024年版)」によると、中小企業の約4割が「VPNを導入していない」または「設定を管理していない」と回答しています。
これでは、社内システムがインターネット経由で直接アクセス可能になり、第三者が内部ネットワークへ侵入できるリスクが高まります。
社外アクセスの増加とリスクの拡大
外出先や自宅から社内ネットワークに接続する社員が増えたことで、通信経路の安全性が課題になっています。VPNを経由せずに接続した場合、通信が暗号化されないため、Wi-Fiスポットなどで通信内容が盗み見られる危険性があります。特にIDやパスワードの入力情報が流出すると、外部からのなりすましログインにつながることがあります。これを防ぐには、強固なVPN環境を整備し、通信経路の暗号化を徹底することが欠かせません。
ファイアウォール設定不備のリスク
ファイアウォールは外部からのアクセスを遮断する装置ですが、設定ミスによりすべての通信を許可したまま運用されている例が見られます。こうした状態では、マルウェアや不正アクセスを検知できず、内部サーバーが直接攻撃を受ける危険があります。企業は、ログ監視やルール更新を定期的に行い、最新の攻撃手法に対応した設定を維持する必要があります。専門業者と連携し、外部監査を受けながら継続的に運用することで、セキュリティ品質を高められます。
内部不正と退職者リスク
VPNやファイアウォールを導入しても、内部要因による情報漏えいを完全には防げません。退職者のアカウントを削除し忘れたり、共有パスワードを複数人が使い続けていたりすることが、思わぬセキュリティホールになります。アクセス権限の棚卸しを定期的に実施し、不要アカウントを削除した記録を残すことが重要です。ここでもデータ消去証明書の発行が有効で、削除履歴を正式に残すことで、監査時の説明責任を果たすことができます。

工場・オフィスのネットワークを守る方法
製造業や物流業など、現場とオフィスが一体化している企業では、通信インフラの安全性が業務継続の要になります。
IoT機器・監視カメラ・センサー・タブレットなど、多くのデバイスがネットワークに接続されており、ひとつの設定ミスが全システムの障害や情報漏えいを招くこともあります。そのため、LAN工事やWi-Fi環境整備、無線設備の点検を含めた総合的な見直しが必要です。
LAN工事・Wi-Fi工事の最適化
LANやWi-Fiは、単なる通信設備ではなく、企業の情報流通を支える基幹インフラです。施工の段階で誤った設計をしてしまうと、通信速度だけでなく、セキュリティにも大きな影響を及ぼします。愛知県をはじめとする製造業の多い地域では、工場とオフィスのネットワークを分離せずに共用している企業も見られ、これが大きなリスク要因になっています。
適切な配線設計とネットワーク分割
LAN工事では、部署や業務ごとに通信を分ける「VLAN(仮想LAN)」の設計が推奨されます。これにより、万一不正アクセスが発生しても、特定の部署にのみ影響を限定できるようになります。さらに、冗長構成を取り入れることで、通信障害時も自動で切り替えが行われ、業務停止を防げます。
これらの設計思想をもとに施工することで、単なる配線ではなく、リスク分散を備えた強固な通信構造を構築できます。
Wi-Fi電波設計と暗号化方式の選定
Wi-Fiネットワークでは、古い暗号化方式を使い続けている企業も多く見られます。特にWEPやWPA2などは既に脆弱性が指摘されており、解析ツールを使えば数分で解読可能なケースもあります。現在主流のWPA3方式に切り替えることで、通信内容の保護レベルを格段に高めることができます。また、SSIDの隠蔽やMACアドレス認証、ゲスト用ネットワークの分離といった多層的な防御を導入することで、外部からの侵入リスクを減らすことができます。
無線設備点検・登録点検の必要性
無線通信機器は、企業の業務効率を支える重要な要素です。しかし、使用年数が長くなるほど機器性能が低下し、通信トラブルの原因となることがあります。そのため、電波法に基づく定期点検・登録点検を行うことが必要です。法令上の義務だけでなく、通信の安定性を保つうえでも、定期的な確認は欠かせません。
定期点検の目的と実施頻度
無線設備点検の目的は、通信の品質と安全性を確保することにあります。総務省では「登録点検制度」を設け、3年以内ごとの実施を推奨しています。点検では、送信出力・周波数のズレ・アンテナの損傷などを確認し、異常がある場合は即時に是正措置を行います。
このような点検を定期的に行うことで、通信障害の予防と法令遵守の両立が実現します。
電波干渉と通信トラブルの実例
オフィスや工場では、複数の無線機器やWi-Fiルーターが混在しているため、電波干渉が起こりやすい環境です。たとえば、隣接する事業所が同じ周波数帯やチャンネルを使用している場合、通信速度が著しく低下したり、接続が不安定になったりすることがあります。このような問題を解決するには、周波数の調整や出力制御を行う定期的な点検が欠かせません。
点検データを蓄積すれば、トラブル発生時の原因分析にも役立ちます。
点検結果の活用と改善サイクル
点検結果は、単なる記録ではなく、今後の通信インフラ改善のための貴重なデータになります。電波強度のばらつきや通信ログを分析することで、アクセスポイントの位置調整や機器更新の時期を判断できます。また、点検報告書を社内文書として保管しておくことで、監査時の法令遵守証明にも利用できます。無線設備の点検を継続的に行うことは、通信の安定性と企業の信頼性を高める投資といえるでしょう。
防災無線・業務用無線の保守と法令対応
防災無線や業務用無線は、災害時の通信手段として欠かせないインフラです。特に愛知県のような産業密集地域では、工場間や自治体間の緊急連絡手段としての無線通信が重要な役割を果たしています。そのため、これらの設備は定期的な保守点検と法令対応を徹底する必要があります。
機器の経年劣化と更新サイクル
防災無線や業務用無線は長期間使用されることが多く、アンテナやケーブル、制御盤などの部品が劣化します。特に屋外設置機器は風雨や温度変化の影響を受けやすく、通信範囲の低下やノイズ混入の原因となることがあります。一般的に、防災無線設備の更新目安は7〜10年程度とされています。機器がメーカーの保守期限を過ぎた場合、交換やリプレイスの検討を早めに進めることが推奨されます。
保守契約による安定運用
保守契約を締結することで、点検・修理・緊急対応を計画的に行うことが可能になります。特に防災無線では、災害訓練時に動作確認を行うなど、定期的な稼働チェックが有効です。業務用無線では暗号化通信の設定や基地局・子機間のペアリング確認など、技術的な保守を並行して行うことで、セキュリティリスクを最小化できます。これらの取り組みは、平常時だけでなく、非常時にも企業活動を止めないための重要な仕組みとなります。
法令遵守とリスクマネジメント
電波法では、無線局の開設者が設備を適切に維持・管理する義務を負うと明記されています。点検記録を残さなかった場合、万が一通信障害が発生しても使用者側の責任が問われることがあります。さらに、防災通信では自治体・消防・警察などとの連携が必要となるため、法令に準拠した運用が前提となります。無線設備の保守は、単なる点検作業ではなく、企業の事業継続計画(BCP)を支える柱といえるのです。

愛知でITセキュリティのことなら株式会社グライドパス
これまで解説してきたように、データ消去やネットワーク整備、無線通信の点検はすべて、企業のセキュリティを構成する連続した仕組みです。どれか一つの対策だけでは十分ではなく、情報の削除・保護・記録を一体化した運用が必要です。その実現において、データ消去証明書(破壊証明書)は信頼を可視化する重要な要素となります。
当社株式会社グライドパスでは、データ消去サービスとデータ消去証明書発行を中核に据えたITセキュリティ支援を行っています。さらに、LAN工事・Wi-Fi工事・無線設備点検など、通信インフラ全般の設計・施工・保守までを一貫して対応しています。これにより、情報資産の廃棄から運用までをワンストップで管理でき、安全性と効率性の両立を実現しています。
愛知に根ざした確かな実績と技術力
愛知県は製造業を中心に、多くの企業が高度なネットワーク環境を必要としています。当社は地域密着のサポート体制を強みに、企業や自治体、教育機関など、多様な現場で通信インフラとデータセキュリティの最適化を進めてきました。特に工場内ネットワークの再構築やIoTデバイスの安全接続など、現場特有の課題に対応する柔軟な技術力を備えています。また、防災無線・業務用無線に関する登録点検や法令対応にも対応しており、通信と安全を両立するトータル支援を提供しています。
データ消去証明書がもたらす信頼の価値
データ消去証明書は、単なる書面ではありません。それは、企業が情報管理を真摯に行っている証拠であり、取引先や顧客に対する信頼の象徴です。監査対応やISMS認証、プライバシーマーク更新の際にも、正式な証跡として提出できるため、内部統制の強化にもつながります。今後、ESGやサステナビリティ経営が重視される時代において、「情報を適切に消す力」こそが企業価値の一部になるでしょう。
当社株式会社グライドパスは、こうした意識をもつ企業のパートナーとして、安心と信頼を届けています。
企業の未来を支えるために
データ消去やネットワーク保守といったITセキュリティ対策は、もはや「専門業者任せ」ではなく、経営戦略の一部として考える時代に入りました。当社株式会社グライドパスは、愛知を中心に、企業が安心して業務を継続できる環境を整備しています。データ消去証明書の発行からネットワーク設計、無線保守まで、あらゆるIT資産の安全をサポートします。愛知でITセキュリティを強化したい企業は、ぜひ当社株式会社グライドパスへご相談ください。
確かな技術と透明性のある証明が、御社の信頼を未来へとつなげます。
Contact
ご相談ください
お見積もりのご依頼や、
ご質問等お気軽にご活用ください
お急ぎの方、
お電話でもお気軽にご相談ください。

